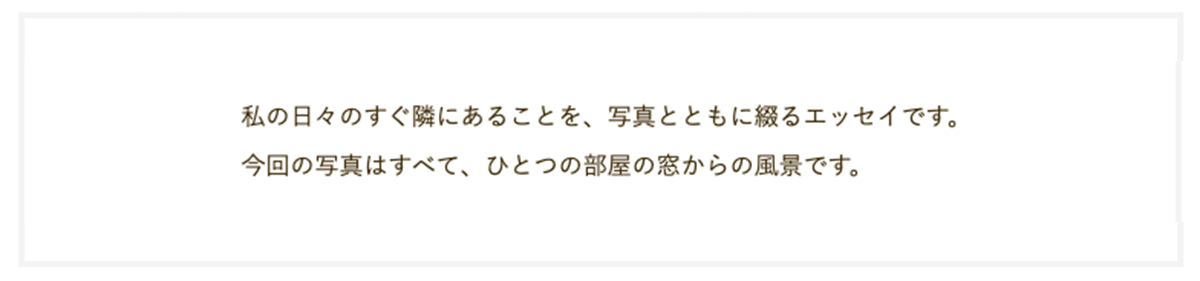『窓』前田エマ vol.2

一緒に暮らしたことのない父親が、結構いいマンションに住んでいるのを知ったとき「この人の部屋の窓からは、どんな景色が見えるのだろう。たぶん我が家のほうがいい景色だろうな」と私は思った。そして、我が家に遊びにくるたびに、父親はどんな気持ちで、我が家の窓からの景色を見ているのだろうか、と気になった。
私の友人がとんでもないお金持ちとお付き合いをしていたときに、その人の住んでいる超高級マンションの最上階へおじゃましたことがあった。私がそのときに驚いたのは窓から見える地面を歩く人々の小ささだった。それは人を見ているというよりも、なんだか蟻を観察しているような気分だった。「もし世界がひっくり返って、すんごいお金持ちになったとしても、高層マンションの最上階には住まないようにしよう」と、私は心に決めた。
私は生まれてからずっと、おんなじ家で暮らしている。私が生まれる前に、母親が購入した普通の中古マンションだ。
私は、家を出たいと思ったことがない。母親と仲がいいのも理由のひとつだと思うのだけれど、この部屋の窓からの眺めが非常に気に入っているのだ。私の暮らすマンションの目の前には、川が流れている。
今年の春は、まぼろしのような春だった。桜が咲いて散っていくのも、4月だというのに雪が降ったのも、そこまでひどくなかった花粉症のことも、草花がどんどん色を濃くしていくのも、私はぜんぶを、部屋の窓からぼけーっと見て感じていた。
いつもだったら野球少年たちが朝早くから練習をしていて大きな声がするはずなのに、その姿はどこにも見当たらなく、その代わりに暇を持て余した社会人の男の人たちがスケートボードを練習している。その、ガリガリとした音が耳障りだった。
経済活動が縮小しているからなのだろうけれど、普段はお目にかかれないような大きな鳥たちが、川へやってきて空を飛び回り、それから逃げるように我が家のベランダには小さな鳥たちがたくさんやってきて、フンをしていった。
雨は苦手なのだけれど、むわんっとする湿気った気配が辺りを包み、それから遠くのほうからさーっと雨音が近づいてきて、ざーっとこちらにやってきたかと思えば、川の水かさがどんどん増していき、夕方になると止んだので窓を開けてみると、水を含んだ土がこれでもかと匂うその空気に、私はとっても嬉しくなってしまった。
この春、私は今までに撮っていた川辺の写真を、何度もスマートフォンの画面で眺めた。目の前の景色が夢の中のようで、スマートフォンの中の世界が現実のような、不思議な気持ちになった。
私の家には、大きな一枚の絵がある。これは、母親がここへ越して来る前に買ったものだ。当時住んでいた部屋の窓からの景色が、彼女はあまり好きではなかったようで、窓の代わりに絵を買ったのだという。次に住むところは、窓からの景色がいいところにすると母親は心に決めていたそうだ。
母親が育った家、つまり私の祖母の家は、雑木林の隣に建っている。私はひんやり冷たい祖母の寝室のベッドに寝転がって、祖母の匂いを吸ったシーツに包まれながら、窓の外で木々が揺れる音や、木漏れ日の移ろいを身体いっぱいに感じることが好きだ。毎週のように顔を見せに行く祖母の家にも、この春は入れなくて、私は祖母の寝室を思い出しながら自分の部屋のベッドの上で昼寝をしまくっていた。
いつかここから離れるときが来ることを、私は想像してみた。どんな家に暮らしたいか、考えてみた。まず、大きな窓がある家がいいな。そして窓から、今日の天気と自分が今いる季節を知ることができるといいな。人の様子が分かるくらい、地面との距離が近いといいな。
そんな妄想を、私は教会の鐘の音を聴きながら、窓から流れ込んでくる夏の匂いを少し含んだ隙間風に当たりながら、このエッセイを書いている。